ESG(環境・社会・企業統治)投資への関心の高まりから、従来の財務関連情報を超えて、企業に求められる開示情報はますます増えている。中でも、気候関連の開示情報については、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)が気候変動への取り組みや影響に関する財務情報の開示に関する枠組みを示し、開示情報のガイドラインを明文化したことで、客観的に企業を比較することが可能となった。また、それを受けて上場企業に対して開示を義務化する動きが加速されたことで、より一層開示への圧力が高まった。
求められる環境関連情報の開示
こうした状況をうけて、企業は関連情報の開示にあたっては、次のような情報を検討し、公表することが期待されるようになっている。
まずは炭素と温室効果ガスの排出量だ。「自社が事業活動で直接的に排出するもの(Scope1)」、「自社が購入する電気、蒸気、熱を発生させるために排出するもの(Scope2)」、さらには「自社の事業活動に必要となる原材料などの調達によるバリューチェーンの上流で発生したものと、自社の商品を販売するといった下流で発生するもの(Scope3)」を、ガイドラインなどによって示されたプロコルに従って算出して、提示しなければならない。自社流ではなく、適切とされる計算基準に基づいたものでなければならないわけである。
二つ目はマテリアリティ(重要課題)である。自社の事業活動に関わり、環境に対して影響を及ぼす要因、そして環境から受ける影響要因を評価し、自社として取り組むべき課題として何を取り上げるのか、ダブル・マテリアリティを示す。事業との関わりで、何を認識し、どのように対応するかを示すことで、投資家がサステナビリティに対する当該企業の姿勢を的確に把握でき、投資判断を下すことにつながる。
しかも、そうして認識した二酸化炭素排出量に対して、パリ協定に従って2050年までに、どのようにして正味排出量をゼロにするかといった道筋を、目標、指標なども伴って示すことも求められている。
リスクマネジメント視点の説明が不可欠に
リスクマネジメントの視点からの対応も不可欠となる。企業の戦略的な方向性に対応して、気候変動に関連して何がリスクであり、何が事業機会になりうるかを判断する。自社のリスク取得意欲に基づいて、どのように対応しようとするのか、戦略的な意図を明確にすることが求められている。リスク、機会、そして経営戦略に関する説明が不可欠というわけだ。
こうした戦略的な対応に向けて、取締役会や外部監査といったガバナンス体制をどのように整備しているのかも示さねばならない。組織全体として気候変動に対して積極的、かつ実効性を伴う対策を、事業展開と軌を一にして実現するためには、ガバナンスが機能していることを証明することが前提となるからだ。
このように高まる企業への社会的要請に対して的確に対応するためには、組織が導入している既存のリスク対策フレームワークでは覚束(おぼつか)ないものと思われる。例えば、「TCFDが示すフレームワークなどを理解することを通して、気候変動リスクをどのように測定して把握し、どのように管理していくべきなのか」、「その際には、どのように指標、目標、移行計画を策定するべきなのか」といったことについて、ベストプラクティス(最適な方法)などを参考にして、既存フレームワークを見直すことが出発点になりうる。
事業計画とリスク対応計画とのプロセス上での連動、シナリオ分析やストレステストなどの具体的なツールの組織的な活用など、リスクマネジメント体制の見直しと改善に向けて前進し、組織としてリスクに対する事前準備態勢を整えなければならない。さらに事後処理対策を強化するという意味でのリスクマネジメント能力の強化が必要となる。
◆RIMS(the Risk and Insurance Management Society)とは
世界最大のリスクマネジメントの非営利組織で、世界に80支部を抱え、75カ国のリスクマネジャー、1万人の会員を擁している。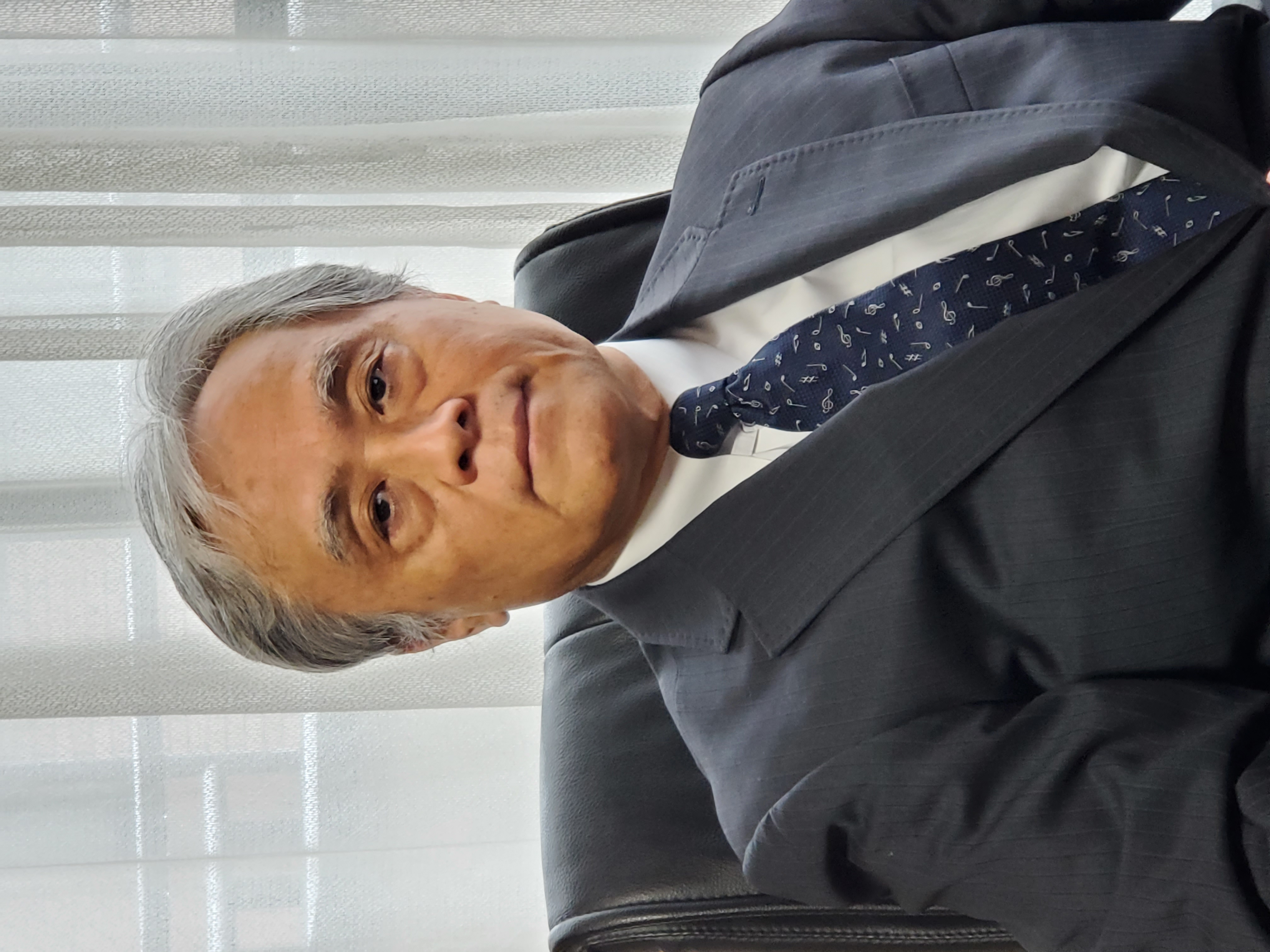 明治学院大学名誉教授
明治学院大学名誉教授1953年長野県生まれ。一橋大学商学部卒業、同大学大学院商学研究科修了。明治学院大学経済学部専任講師、助教授、教授を経て、2022年3月定年退職。経営戦略論、経営組織論、労務管理論などを専門とする。経営戦略を中心にグローバル化、ISOマネジメントなど幅広い研究領域に関心を持つ。東京商工会議所中央支部老舗企業塾の創設に参加し、日本生産性本部や日本科学技術連盟での調査研究や、企業内経営スクールでの講師を務めるなど、実務と結びつく研究に重きを置いている。現在は、(一財)リスクマネジメント協会理事長、米国RIMS(the Risk and Insurance Management Society)日本支部支部長、生産性本部生産性運動基盤センター総括アドバイザーなどを兼任。

